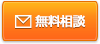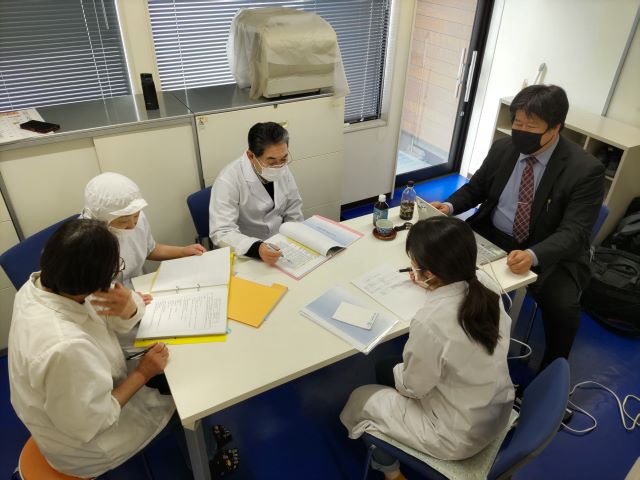FSSC22000 v6.0 と JFS-C v3.2 の違いとは?
投稿日:2025年11月24日 最終更新日:2025年11月25日
Contents
FSSC22000 v6.0 と JFS-C v3.2 の違いとは?
こんにちは!ISOコム株式会社 芝田 有輝です。
今回は、FSSC22000 v6.0 と JFS-C v3.2 の違いとは? について、お話ししてみたいと思います。
個人的な感想も含んでいますので、比較の参考情報として活用いただけましたら幸いです。
では早速、行ってみましょう!
■0. 規格毎の概要
- FSSC22000
→ 「世界で通用する、フル装備の国際免許」 - JFS-C
→ 「日本国内で乗るには十分な、国産免許」
どちらも「安全に運転する」=**食品安全のしくみ(FSMS+HACCP+衛生管理)**を作るための規格です。
ただし、
- 世界の大手メーカー・海外の取引先も視野に入れるなら、FSSC22000をベースに考えておく方が“将来の伸びしろ”が大きい
- まず日本国内で認証を取りたい、社員もHACCP超初心者という場合は、JFS-Cの方がとっつきやすい
というイメージです。
■目次:
- 用語説明
- FSSC22000とJFS-Cの「中身の構成」
- マネジメント(FSMS)の違い
- HACCPの違い
- 衛生管理(PRP/GMP)の違い
- FSSCだけ重いところ/JFS-Cだけ特徴的なところ
- 最後に「どっちを選ぶ?」の目線で整理
■1. 用語説明
- FSMS(食品安全マネジメントシステム)
→ 「会社全体で食の安全を管理するための、仕組み・ルール・記録のセット」
例:目標、責任分担、教育、内部監査、改善 など - PRP(前提条件プログラム)
→ 「HACCPを動かすための土台となる衛生管理・設備管理」
例:清掃・殺菌、害虫駆除、ゾーニング、手洗いルール、服装、設備点検 など - HACCP
→ 「危険になりそうなポイントを事前に洗い出して、そこで必ず安全をチェックする」しくみ
例:加熱温度・時間、冷却温度、金属検出機 など
この3つの組み合わせで、
「会社としてどう管理するか(FSMS)」+「現場の日々の衛生管理(PRP)」+「製造ラインの危険ポイント(HACCP)」
をまとめているのが、FSSC22000やJFS-Cです。
■2. 中身の構成
2-1 FSSC22000(Version 6.0)の中身
- ベース:ISO22000:2018(4〜10章)
- プラス:ISO/TS 22002-x、PAS221など、業種ごとの衛生管理(PRP)
- さらに:2.5.1〜2.5.18の“追加要求”
- フードディフェンス(悪意ある混入対策)
- フードフラウド(不正混入対策)
- アレルゲン管理
- 環境モニタリング
- 食品ロス・廃棄の管理
- マルチサイトの管理 など
イメージ:
「ISO22000(本体)+ 厚めの衛生ルール集 + 世界の要求を反映した追加ルール集」
2-2 JFS-C(Version 3.2)の中身
- FSM(1〜27):FSMS=会社全体のマネジメント
- HACCP(Step1〜12):Codexの12ステップそのまま
- GMP(1〜…):衛生管理・設備管理(PRP)
特徴:
- ISO22000:2018の構造や考え方に基本的に沿っている
- 文章が日本語で具体的(「ゴミ・雑草」「カイゼン提案」などイメージしやすい)
- 「日本の食品法令としっかり紐付くように書かれている」
イメージ:
「ISO22000を日本語でかみ砕き、日本の現場向けに具体的にした国産パッケージ」。
■3. FSMS(マネジメント)の違い
3-1 共通部分
- 会社の状況・課題を把握する
- トップが方針と目標を決める
- リスクと機会を考える
- ルールと記録を作り、教育し、運用する
- 内部監査やマネジメントレビューでチェック
- 不具合を直し、改善を続ける
というPDCAの回し方はほぼ同じです。
3-2 FSSC22000が重くなりやすいポイント
- 品質も一体で見る(2.5.9)
- 食品安全だけでなく、「品質方針・品質目標・品質内部監査」も求められる
→ ISO9001まではいかないが、それに近いことも一緒にやるイメージ
- 食品安全だけでなく、「品質方針・品質目標・品質内部監査」も求められる
- 追加要求(2.5.x)が複数ある
- フードディフェンス、フードフラウド、環境モニタリング、食品ロス、マルチサイト…など
→ 「世界の大手顧客が気にしているテーマ」を先取りしている分、考えること・書くこと・記録が増える
- フードディフェンス、フードフラウド、環境モニタリング、食品ロス、マルチサイト…など
- 多拠点管理(マルチサイト)に具体的なルール
- 本社でどう監督するか
- 各拠点の内部監査をどう回すか
→ チェーン展開している企業ほどFSSCの強みが出るが、負荷も増える
3-3 JFS-C(FSM)が分かりやすいポイント
初心者・中小企業にとって好ましい点は:
- 法令とのつながりが日本語でハッキリ書かれている
→ 「製造国+販売国の法律を守る」ことがストレートに伝わる - カイゼン提案の仕組み(FSM27)を追加要求(FSSC22000にはない)
→ いわゆる日本流の「小さな改善」をシステムに組み込む前提
→ 現場との距離が近い中小企業ほど、現場力をそのまま活かしやすい - 文書化・記録のルールがISO9001っぽく整理されている
→ 既にISO9001を持っている会社は、感覚的に理解しやすい
■4. HACCPの違い(ほぼ同じ)
共通のイメージ
- 危険(ハザード)を洗い出す
- どこで確実に止めるか(CCP)を決める
- 基準(温度・時間など)を決める
- ちゃんと守れているか監視する
- ダメだった時にどうするか決める
- 全体を定期的に検証・見直しする
これはFSSCもJFS-Cもほとんど同じです。
違いの“分かりやすさ”ポイント
- FSSC(ISO22000)側
- 「CCP」と「OPRP」という2種類の“管理ポイント”を使い分ける考え方
→ 理解に少し慣れが必要(教育コスト)
- 「CCP」と「OPRP」という2種類の“管理ポイント”を使い分ける考え方
- JFS-C側
- Codex HACCP 12ステップをそのままStep1〜12で書いてある
- 各ステップに「何を決める・何を記録するか」が整理されている
→ 教育テキストとして使いやすい
実務の重さはほぼ同じです。
■5. PRP/GMP(衛生管理)の違い
ここが、現場から見て一番“負担差”が出るところです。
5-1 FSSC22000(ISO/TS 22002-x+2.5.x)
- ISO/TS 22002-1(食品製造)など、英語の詳細ルール集がベース
- そこにFSSCの追加要求が乗る:
- 環境モニタリング
→ リステリアやサルモネラなど、環境菌を決めた方法で定期的にチェック - PRP検証
→ 清掃・殺菌・ゾーニング・設備管理などの「土台ルール」が、ちゃんと効いているか定期的に確認・分析 - 異物検出機器の要否評価・正当化
→ 金属検出機/X線/マグネットが必要かどうか、“なぜそう判断したか”まで文書化 - アレルゲン管理をかなり細かく要求
→ 洗浄の検証、ラベルの整合性チェック、レビュー頻度など
- 環境モニタリング
→ RTE製品(調理済み食品)や、海外大手向け製造ではかなり評価される一方、現場の仕事は増える、というイメージです。
5-2 JFS-C(GMP)
- 要求レベルは概ねFSSCと同じ方向を向いている
- ただし文章は
- 日本語で具体的(ゴミ・雑草・害虫の表現など)
- 頻度や分析レベルは「ある程度、会社に任せる」余地もある書き方
- “中小〜中堅企業が、現実的に回せるレベル感”を意識している印象
→ 結果として、「ギリギリまで国際レベルに合わせたFSSC」 vs 「日本の現場が回しやすいJFS-C」という差になりやすいです。
■6. FSSCだけ負荷のある箇所/JFS-Cだけ特徴的な箇所
6-1 FSSC22000だけ負荷高め(=強みでもある)ところ
- サービス・購買・試験機関管理(2.5.1)
→ 「原料を買うとき」「試験を外注するとき」「急な代替購入」のルールとリスク評価を細かく求める - ラベル・表示・印刷材料管理(2.5.2)
→ 表示ミスや錯誤が起きないように、かなりしつこくチェックと裏付けを要求 - 品質マネジメント(2.5.9)
→ “食品安全だけでなく品質も一緒に見る”考え方 - 環境モニタリング(2.5.7)
→ 病原菌などのリスクに応じて、汚染状況を定期的に測る - 食品ロス・フードロス/副産物管理(2.5.16)
→ SDGsやCSRを意識した、「捨てる・再利用する」時の安全確保と方針 - マルチサイト(2.5.18)
→ 多拠点の一括管理のルールがかなり具体
これらは、
「海外の大手顧客やグローバルチェーンが気にしていることを、先回りして全部やる」というイメージです。
負荷はありますが、“海外お客様に通用する安心材料”にもなります。
6-2 JFS-Cだけ特徴的な箇所
- カイゼン提案(FSM27)
→ 「現場からの改善アイデアを集め、食品安全に活かしましょう」という条文
→ 日本の中小企業がもともと得意な文化を、そのままシステムに乗せやすい - 日本の食品法令との紐付けが分かりやすい
→ 行政の監査や、国内取引先への説明にとても使いやすい - 用語・構造が日本語で整理されている
→ 「現場教育用テキスト」としてそのまま使えるレベル
■7. 選ぶ基準の整理
7-1 FSSC22000を選ぶ基準
- 今後、海外のお客様や海外グループ会社との取引を視野に入れている。
- 品質(クレーム・歩留まり・仕様)も一緒に管理したい
- 将来的に
- OEM/PB品の輸出
- 海外の有名ブランドとの取引
- 複数工場
を視野に入れている
→ こういう会社様でしたら、
「最初からFSSC22000で作っておいた方が、後で“世界対応オプション”を付け足す手間が少ない」
ので、負荷は高くても長期的には得なケースが多いです。
7-2 JFS-Cを選ぶ基準
- 生産のほとんどが日本国内向け
- 工場規模は単一工場~2〜3工場くらい
- HACCPもISOもほぼ初めてで、現場メンバーも衛生管理の基礎からという状態
- とにかく、
- 「まず認証を取って取引先の要件をクリアしたい」
- 「現場の意識を上げたい」
という 第一ステップが目的
→ こういう会社様でしたら、
「JFS-CでHACCP+FSMS”をまず作る」
→ 数年後、必要になったらFSSCにステップアップ
というルートが現実的です。
一方で、審査機関数は、JFS-C規格が登場した当初から数社減り、現在2社のみ。認証件数は120件
7-3 FSSC22000のメリット
- 世界共通言語になる
- 海外のバイヤーや大手チェーンに対して、説明が1回で済む。
- 「FSSC22000認証」と一言で、求められる水準が伝わる。
- 後から上乗せ対応が少なくて済む
- 今後さらに
- フードディフェンス
- フードフラウド
- 環境モニタリング
- SDGs(フードロス)
を取引先から求められる流れは、今後間違いなく強まる傾向にあります。
- FSSCなら、最初からその辺まで含めて仕組みを作るので、
「後でまた別で管理」「別のシステムを増やす」が減る。
- 今後さらに
- 「食品安全+品質」を一体管理しやすい
- 品質トラブルも、食品安全トラブルも、
同じ枠組み(方針・目標・内部監査・是正)で扱えるので、
経営層・品質部門にとってはマネジメントしやすい形になる。
- 品質トラブルも、食品安全トラブルも、
- 将来の採用力・ブランド力にもつながる
- 若い人材・技術者にとって、
「世界レベルの規格を運用している工場で働いている」ことは
キャリアとしても価値がある。 - 会社としても「グローバルスタンダードの食品安全」を掲げやすい。
- 若い人材・技術者にとって、
■8.まとめ
- どちらの規格も「食を安全にするための仕組み」を作る規格
- 中身(FSMS+HACCP+衛生管理)の考え方は、ほぼ共通です。
- FSSC22000は、世界の取引を見すえた「フルスペック版」
- 追加要求が多く、最初はしんどいかもしれませんが、
- 一度きちんと作り込めば、**海外顧客・多拠点展開・品質管理まで含めて、“あとから困りにくい”**という大きなメリットがあります。
- JFS-Cは、日本語で分かりやすく、国内向けに始めやすい規格
- まず1歩目を踏み出すには、良い選択肢です。
いかがでしたでしょうか。
FSSC22000 v6.0 と JFS-C v3.2 の違い について、ご理解いただけましたでしょうか。
ISOコムへのお問い合わせ
今後の改訂によっては、当社のようなコンサル会社にお問い合わせが殺到する可能性があります。
そのため、安心してISO9001の改訂を終えたいというお客様は、事前に弊社へのコンサル依頼をご予約することもご検討ください。
*ISOコム株式会社お問合せ窓口* 0120-549-330
当社ISOコム株式会社は各種ISOの新規取得や更新の際のサポートを行っているコンサルタント会社です。
ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方はぜひご連絡下さい。